「ほめることも叱ることもしてはいけない」
アドラー心理学では大切な考えだけど、そんなことできるか!!!!
どうすればいいんだ。
その悩みを解決してくれるのが、本著『幸せになる勇気』です。
前作『嫌われる勇気』で自立の大切さを学んだ私たちは、この続編で「愛すること」こそが本当の幸せへの鍵だと知らされます。
教育者として、親として、そしてひとりの人間として、人とのかかわり方を考えていきましょう。
目次
「幸せになる勇気」とは、愛する勇気のこと
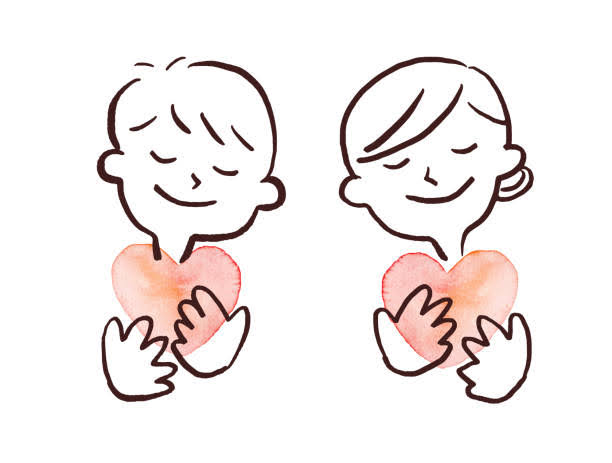
『幸せになる勇気』の結論は明快です。
幸せになるには「愛する勇気」が必要である。
アドラー心理学の本質は、単なる「対人関係のテクニック」ではありません。
他者とどう関わり、どう信じ、どう生きていくか。その根底には「愛」があります。
教育とは、自立のための援助である
アドラーの「課題の分離」は教育には不向きでは?という問いに対して、著者はこう語ります。
教育とは、希望である。
教育とは、介入ではなく、自立のための援助です。
そして、その入り口はその人を尊敬する。
- 子どもを「操作する」のではなく「信じて見守る」
- 教師の権威ではなく、子どもとの信頼関係でつくる学級
- 学級は、一つの民主主義国家である

縦の関係を作るのではなく、横の関係で援助を行う。そのためには、まずは相手を無条件に信じる。相手が信じてくれることは課題の分離で自分の課題ではありません。自分がまず行うことが大切だと気づかされました。
問題行動には段階がある
子どもの問題行動には5段階あると本書は語ります。

- 称賛の要求:「ほめてほしい」「特別でありたい」
- 注目喚起:「悪くてもいいから目立ちたい」
- 反抗:「反抗しても、権力争いで存在を示したい」
- 復讐:「こんなに傷ついた自分を見てほしい」
- 無能の証明:「自分は無力だと演じ、責任を他者になすりつける」
→特に3「反抗」までの段階での対応することが大切になります。
「叱る」ことでさらにエスカレートさせてしまう可能性もあります。
- ほめすぎることで、競争が生まれ、仲間が敵になる
- 他者の承認ではなく、自らの価値に気づかせることが「自立」
この視点から、「ほめる」のではなく、「勇気づける教育」の大切さを痛感しました。
「信じる」ことからすべてが始まる

相手を信じるかどうかではなく、自分がまず信じる。
- 信頼とは、受け身ではなく「能動的な決意」
- 与えなければ、始まらない
- 与えよ、さらば与えられん
私自身、「相手が変わったら信じよう」と考えていたことに気づかされました。相手は影響の輪の外にいます。自分がコントロールできるのは自分だけです。
まず信じるという行為こそが、自分を変えるのです。
人生の主語を「わたし」から「わたしたち」へ
本書の最大のメッセージはこれです。
幸せになる勇気とは、愛する勇気のこと。
- 愛は感情ではなく、決意であり、選択である
- 他者を愛することで、自己中心性から脱却する
- 「わたし」でなく「わたしたち」を主語に生きる
- 共同体感覚を持ち、自分の人生を主体的に生きる

アドラーは、人生を「所属感」と「貢献感」でとらえます。
他者に関心を持ち、他者とともに生きる。
この視点があるからこそ、人は孤独から抜け出せるのだと実感しました。
【まとめ】
『幸せになる勇気』は、「教育」「対人関係」「人生のあり方」にまで踏み込んだ一冊です。
特に心に残ったポイント
- 教育とは、自立のための援助
- 問題行動には段階があり、勇気づけが重要
- 信頼は、まず自分から始めるもの
- 幸せとは、愛する勇気を持つこと
- 人生の主語を「わたし」から「わたしたち」へ
この本を通じて、「人を信じること」や「愛すること」が、どれほど自分自身を自由にするかを学びました。
自分からまずは相手を無条件に信頼をし、人の援助を行っていく。そのことが、他社貢献につながり、相手も自分自身も幸せを感じられる。そうして、ともに生きる者として社会をよりよいものにできたら最高だなと感じました。

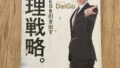

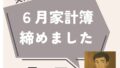
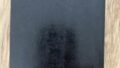
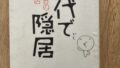
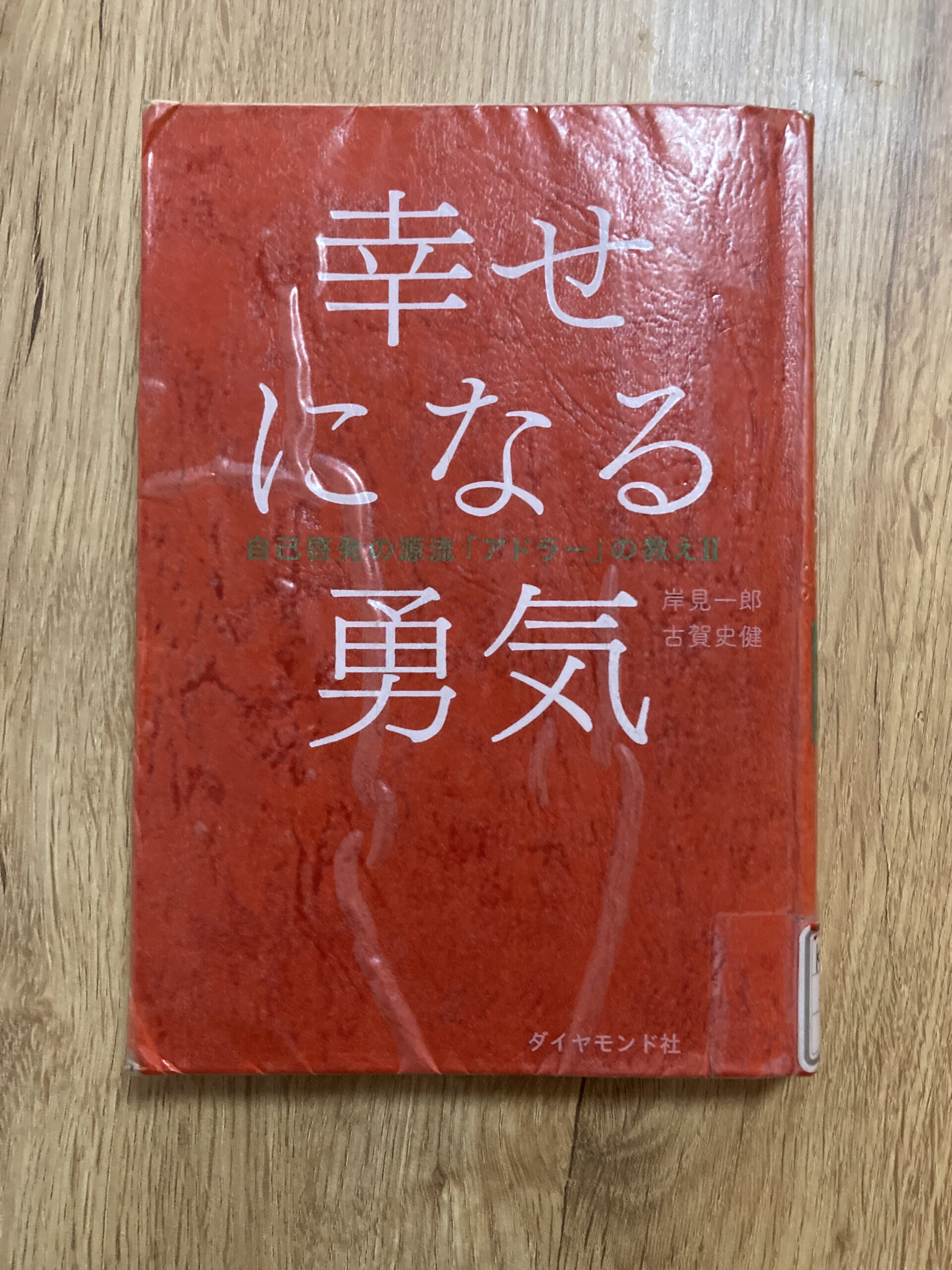


コメント